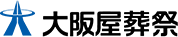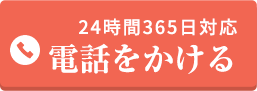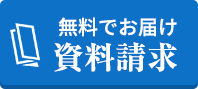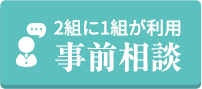香典とは?
香典とは、故人へのお悔やみの気持ちを込めて、お線香やお花の代わりにお供えする金品のことです。遺族が負担する葬儀費用の助けとなる意味もあります。香典を渡す際には、袱紗(ふくさ)の使い方や金額のマナーなど、いくつかの注意点があります。今回は、香典の基本から包み方、書き方まで詳しく解説します。
香典を渡す際のマナー
1. 袱紗(ふくさ)の選び方
香典を包む際には、袱紗を使用するのが正式なマナーです。葬儀で使用する場合は、寒色系・暗色系の袱紗(紺・グレー・紫など)が適しています。特に濃い紫色の袱紗は、弔事・慶事の両方に使えるため、一つ持っておくと便利です。
- 略式の袱紗(二つ折りの金封袱紗)は、包む金額が多い場合には不向き
- 無地のハンカチや風呂敷でも代用可能(ただし派手な色柄は避ける)
2. 袱紗での香典の包み方
香典を包む際は、袱紗を菱形に広げ、中央よりやや右側に香典袋を置きます。その後、右→下→上→左の順番で包みます。
※弔事(葬儀)は左開き、慶事(結婚式など)は右開きになるように注意しましょう。

香典袋の書き方
香典袋は「外袋」と「中袋」に分かれています。一般的な香典袋には、薄墨を使用して書くのがマナーです。(ただし、一部地域では薄墨を使用しない場合もあるため事前に確認すると安心です。)
1. 外袋(表書き)の書き方
香典袋の表面には、上段に「表書き」、下段に「氏名」を記入します。
- 仏教の場合
- 「御霊前」:通夜・葬儀の際に使用
- 「御仏前」「御佛前」:四十九日以降に使用
- 「御香典」:宗派を問わず使用可能
- 浄土真宗では「御霊前」を使用せず、「御仏前」や「御香奠」が適切
- 神式の場合
- 「御神前」「御玉串料」「御榊料」
- キリスト教の場合
- カトリック:「御花料」「御ミサ料」
- プロテスタント:「御花料」「献花料」「弔慰料」
2. 外袋(氏名)の書き方
表書きの下段には、氏名をフルネームで記入します。肩書きをつける場合は、氏名の右側に小さめに書きましょう。
3. 中袋の書き方
香典袋の中袋には、お金を入れます。記入する内容は以下の通りです。
- 表面:金額(旧漢数字を使用)
- 3,000円 → 参仟圓
- 5,000円 → 伍仟圓
- 10,000円 → 壱萬圓
- 50,000円 → 伍萬圓
- 100,000円 → 拾萬圓
- 裏面:郵便番号・住所・氏名
- 中袋の裏面には、送り主の郵便番号・住所・氏名を記入します。
- 遺族が誰からの香典かわかるよう、はっきりと書きましょう。
香典の金額のマナー
香典の金額は、基本的に**「奇数」にするのがマナーです。偶数の金額は「割り切れる」=「縁が切れる」**とされ、弔事には不適切と考えられています。
香典の相場
包む金額は、故人との関係性によって変わります。地域差もあるため、事前に確認すると良いでしょう。
| 故人との関係 | 一般的な相場 |
|---|---|
| 両親 | 5万~10万円 |
| 兄弟姉妹 | 3万~5万円 |
| 親戚 | 1万円~3万円 |
| 友人 | 5千円~1万円 |
| 勤務先関係 | 3千円~5千円 |
付き合いの深さによって、相場より多く包むこともあります。ただし、あまりにも高額すぎると遺族に気を遣わせてしまうため、適切な範囲内で包むようにしましょう。
まとめ
香典は、故人へのお悔やみの気持ちを込めた金品であり、遺族の葬儀負担を軽減する意味もあります。香典を渡す際には、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
✅ 香典袋は袱紗に包み、寒色系・暗色系を選ぶ
✅ 表書きは宗教ごとに適切な言葉を使用する
✅ 金額は奇数にする(3千円・5千円・1万円など)
✅ 中袋には金額・住所・氏名を明記する
✅ 包む金額は、故人との関係性によって相場を考える
香典のマナーを正しく理解し、故人とご遺族に心を込めたお悔やみを伝えましょう。
香典のマナーについて詳しく知りたい方や、葬儀に関するご相談は大阪屋葬祭へお気軽にお問い合わせください。