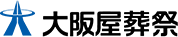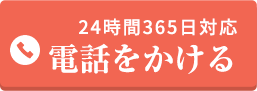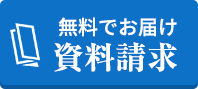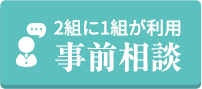喪主とは?
遺族を代表して葬儀全体を取り仕切る人のことを喪主といいます。
喪主は、葬儀に関する最終決定権を持ちます。
葬儀に関する最終的な決定権を持つ重要な役割を担いますが、喪主について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、喪主の役割や決め方について詳しくご説明いたします。
喪主は誰が務めるべきか
喪主を誰が務めるべきなのか。明確なルールや規定はありません。
それぞれの家庭の状況や故人との関係をふまえて家族で話し合い、決める形で問題ありません。
故人の遺言で喪主の指定があった場合は、それに従って喪主を決めることになります。
一般的な慣習では、故人の配偶者か長男が喪主になります。
しかし、配偶者が高齢であったり病気であったりして喪主を務めるのが困難な場合や、長男不在の場合は、血縁関係の深い方が優先されます。
故人に配偶者や血縁者がいない場合、知人や友人が喪主を務めることもあります。
家庭ごとの事情や状況に応じて柔軟に決められるため、事前に話し合いをしておくことがおすすめです。
喪主の役割とは?
- 葬儀会社への連絡・選定
葬儀の準備を始めるため、葬儀会社を選び連絡をします。喪主を中心に、葬儀の形式や規模、日時などを計画します。 - 菩提寺や関係者への連絡
お付き合いのある菩提寺に連絡し、日程を調整します。また、親戚や知人、友人への訃報連絡も喪主の重要な役割です。 - 葬儀での対応
葬儀当日は、親族や参列者、ご僧侶への対応を行います。さらに、喪主として葬儀中に挨拶をする場面もあります。
これらの役割を通して、葬儀全体を取り仕切る中心的な存在となるのが喪主です。
喪主の負担を減らすために
喪主は多くの役割を担うため、心身ともに負担が大きくなることがあります。大阪屋葬祭では、喪主の方の負担を少しでも軽減できるよう、全面的にサポートさせていただきます。
まとめ
遺族を代表して取り仕切る人のことを喪主といいます。
喪主は葬儀に関する最終決定権を持ちます。
誰が務めるべきという明確なルールはありません。
故人の遺言がなければ、家族などの血縁者が務めます。話し合いによって決める形で問題ありません。
喪主は葬儀の形式や場所の決定、参列者への連絡などさまざまな役割があります。
大阪屋葬祭では喪主の負担を少しでも軽くできるよう、精一杯サポートさせて頂きます。
また事前に葬儀の相談をすることによって負担が軽くなることもあります。
ぜひ、お気軽にご相談ください。